

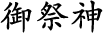
武甕槌命
国譲りで大国主命の子健御名方神に勝ち、国譲りをなし遂げた神です。
勝運・産業繁栄・交通安全などの御神徳があるとされています。
経津主命
武甕槌命と共に国譲をなし遂げた神です。
経津は剣の切る勢いを示し、勇武をあらわしているとされています。
勝運・交通安全・国家鎮護・諸産業の繁栄などの御神徳があるとされ、災難除けの神でもあります。
天児屋根命
春日権現・春日大明神とも称される祭祀を司る神です。
国土安泰・産業繁栄・家内安全・交通安全、智育守護など常に国政に参与して、国土経営に大きく貢献しました。
姫大神
天児屋根命の妃神。

大同4年(809)、現在の三笠山に霊光が雷鳴と稲光の如くなること連夜に及び、人々はその形状を窺うことすらできませんでした。
その中、勇悍にして物怖じない兵部卿が、直ちに訪れてその正体を窺うと、白髪の老翁が白鹿に騎り、忽然として楢の大木の下に現れ、兵部卿に宣ります。
「我は是れ三笠山に住める翁ぞ」と告げ、南東方向に飛び去りました。奇異の思いをなした兵部卿は、これぞ奈良の春日大明神の霊験に違いないと御神徳に感佩し、直ちに宮殿を造営し、春日四神を鎮め奉りました。
この時より当社山を三笠山と唱へ、楢の木を御神木と定めました。
鎮座以来、社殿の修理、年中の祭祀など怠ることありませんでしたが、寿永・元暦・文治(1182-1190)の頃、賊徒によりいくつかの社殿などが悉く破却されます。
建久7年(1196)大友能直が豊前・豊後両国の守護職、及び鎮西奉行となってからは、大友氏から代々の尊崇を加え、神田等が寄附されました。また、承元2年(1208)には獅子形一対、翁面一面が奉納されました。
由緒記では、藤原定家の弟・暁月の作と伝えており、今も社庫に秘蔵されています。
大友氏の幕下の内藤主馬が当地に居住した時、祭殿を奉建して毎歳十二度の祭祀を始め、建長4年(1252)再び社殿を造営。
同5年(1253)下川面に御旅所を構えて、神輿を始め神具等を新たに調進して馬場先川向いに神庫を造営して納めました。
それ以来、その古跡は「御蔵の本」と称されました。そして同7年(1255)10月9日に初めて下川面への神幸が奉斎されました。
その後、大友氏の幕下で大友氏・古庄氏一族である草地氏が居住する采地となり、この時に草地氏は伊豆守に任ぜられたと伝えられています。
祭事を厳重に執行して、その子の草地勘解由介も奉幣と尊崇を怠ることありませんでした。
しかし、天文元年(1532)10月9日の祭礼にて、流鏑馬が近広まで狂走して頓死し、鞍の落ちた場所を鞍迫と称したとされています。当時の人々は不吉なことだと噂し、その行く末に暗い影を落とします。
天文19年(1550)になるとキリスト教に肩入れした大友宗麟が大友氏21代目の当主となります。それ以降、大友宗麟は領内の数々の神社を破却し、神領等を掠奪します。
当社のその例外に漏れることなく、四殿並立の本殿の他、境内・境外の社殿も悉く煙燼に罹り、神領も没収されて神幸祭祀も廃絶しました。
それまで奉仕していた禰宜、神職も処々に離散し、落魄しました。往年の神田[油田・花神楽田・三月田・祇園田・川面畑]も名前が残るのみとなり、御旅所と御蔵所も手を離れて公田となりました。
ただ御旅所には小塚に小祠が祀られ今に伝えられています。
天正5年(1577)村の氏子が力を合せて、宝殿一宇を旧地に再建し、往年は四殿に鎮座していた四柱の神を同殿に奉斎します。
慶長5年(1600)当地は細川忠興の所領となり当社を尊崇し、数度の奉幣があったとされています。慶長9年(1604)神殿、拝殿、神供屋、神楽殿、社門等を建立。
慶長13年(1608)神供屋、神楽殿門等を建立されます。寛永9年(1632)細川氏が熊本藩に移封し、松平重直が龍王城跡地に龍王陣屋を構えて入封し、同年に神殿、拝殿、神供屋、神楽殿、社門等が造替されます。
寛文9年(1669)からは福知山城主の松平忠房が島原藩主となり、島原領の飛地になってからも崇敬を集め、安政元年(1855)神幸祭を再興し、祭式も全て旧に復しました。
明治6年(1873)郷社に列格。全村氏子にして尊崇浅からず、明治39年(1906)神饌幣帛料供進神社に指定されます。
また明治40年(1907)大分県知事から地名を、奈良の御本社(春日大社)と同様の名称である「西国東郡草地村三笠山」の使用が認可され、内外の崇敬をうけて今日に至っています。
平成14年(2002)に氏子崇敬者を挙げて「平成の大改修事業」として、
拝殿ほか3棟の古代本瓦による屋根の葺替え、御旅所の尾園神幸殿、神輿蔵の建て替え、本神輿の新調、『三笠山春日神社誌』の刊行などが行われました。
平成23年(2011)10月28日には、平成14年(2002)に倒壊の危険からやむなく立て替えられた神輿蔵と尾園神幸殿を除く、全ての木造建物11件と、
参道鳥居並びに西参道鳥居の合計13ヶ所が国指定登録有形文化財として登録されました。
なお、当社の境内は三笠山のほかに、秋季大祭で御神輿が一泊される尾園の神幸殿、豊後高田市の史跡である呉崎の潮汲斎場と、約7,000坪を有しており、名実ともに西国東を代表する神社のひとつです。