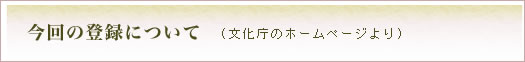 |
 |
文化庁のホームページのなか、「文化財」から以下を抜粋掲載して
概要の説明とします。 |
 |
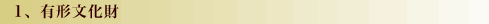 |
| 建造物、工芸品(以下中略)などの有形の文化的所産で、我が国にとって歴史上、芸術上、学術上価値の高いものを総称して「有形文化財」と呼んでいます。このうち、国が指定する国宝・重要文化財と国が登録する登録有形文化財とがあります。 |
 |
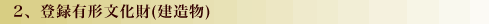 |
平成8年10月1日に施行された文化財保護法の一部を改正する法律によって、保存及び活用についての措置が特に必要とされる文化財建造物を、文部科学大臣が文化財登録原簿に登録する「文化財登録制度」が導入されました。
この登録制度は、近年の国土開発や都市計画の進展、生活様式の変化等により、社会的評価を受けるもまなく消滅の危機に晒されている多種多様かつ大量の近代等の文化財建造物を後世に幅広く継承していくために作られたものです。届出制と指導・助言等を基本とする緩やかな保護措置を講じるもので、従来の指定制度(重要なものを厳選し、許可制度の強い規制と手厚い保護を行うもの)を補完するものです。 |
 |
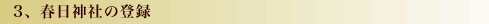 |
| 文化審議会(会長 西原鈴子)は、平成23年7月15日開催の同審議会文化財分科会の審議議決を経て、新たに178件(このうち春日神社13件が含まれます)の建造物を登録するよう文部科学大臣に答申を行いました。 |
 |
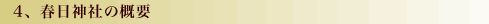 |
文化庁が発表している『登録有形文化財一覧表』のうち「名称」「建設年代」
「特徴等」について、春日神社に関する部分を転載します。尚、建設年代に
ついてはかっこ書きで当社由緒によるものを参考として記しています。 |
 |
| ■名称と建設年代 |
| 春日神社本殿 |
江戸末期 |
(文化7年か 1810) |
| 春日神社摂社厳島神社 |
明治期 |
|
| 春日神社摂社八坂神社 |
江戸後期 |
(延享年間か 1744頃) |
| 春日神社申殿 |
明治38年 (1905) |
|
| 春日神社拝殿 |
大正10年 (1921) |
|
| 春日神社籠り屋 |
昭和 2年 (1927) |
|
| 春日神社神楽殿 |
天保 6年 (1635) |
|
| 春日神社鐘楼 |
文政13年 (1830) |
|
| 春日神社神門 |
弘化 2年 (1845) |
|
| 春日神社西門 |
江戸後期 |
(文政元年か 1818) |
| 春日神社余興舞台 |
昭和27年 (1952) |
|
| 春日神社参道鳥居 |
享保 5年 (1715) |
|
| 春日神社西参道鳥居 |
昭和 9年 (1934) |
|
 |
|
 |
| 豊後高田市の北郊、三笠山の西麓に境内を構える古社である。境内中央に本殿が鎮座し、その前面に申殿と拝殿を連ねて中軸とし、また本殿の東西に八坂神社と厳島神社を祀る構成で、県内で類例のみられる特徴的な社殿配置をとる。本殿は建ちの高い切妻造三間社で、妻飾りを二段に持ち出し、組物などに巧緻な彫刻を施すなど入念なつくりで、向拝のアーチ型虹梁も独特である。拝殿は東西九間と横長で、中央に入母屋屋根の向拝を構える。内部は一室で特に本殿側を開放的な構成としている。拝殿前方の参道東側には、能舞台のように橋掛を備えた神楽殿が建ち、参道西側には袴腰付の鐘楼を建て、また参道正面には重厚なつくりの神門を構えるなど、多様な堂社が趣のある境内を形成している。この他、境内西方の集落にある御旅所には、前面を吹放した農村舞台形式の余興舞台が保存されており、神社と民衆との結びつきを伝えている。 |
 |